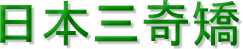 錦帯橋(岩国)蔓橋(祖谷)猿橋(大月)
錦帯橋(岩国)蔓橋(祖谷)猿橋(大月)
| 日本三奇矯は、一般的には錦帯橋・かずら橋・猿橋と言われていますが、特に定義が有るわけではありません。*昔の街道(江戸時代)に近く、*知名度や利用頻度、*現存しているか。などの観点から、現地を見て感じたのは、錦帯橋と猿橋については異論は少ないと考えますが、かずら橋については構造や材料等の違いで異論もあると思います。宇奈月町の黒部川に掛かる、愛本刎橋は猿橋と構造が似ており(猿橋を保守管理している方から刎橋の構造をいろいろと教えていただいた)奇矯にふさわしいと考えますが、昭和44年8月の豪雨で流出し現存していません、従って現状では三番目の奇矯はかずら橋で良いのでは無いかと思っています。 |
祖谷のかずら橋 シラクチカズラの吊橋 |
||
 |
 |
 |
| 猿橋 橋脚を持たない桔橋 | ||
 |
 |
 |
 |
 |
猿橋は桂川の両岸が崖となって幅が狭く、水 面から高い位置にあるため橋脚が立たず、架橋 するには吊橋か刎橋となる。刎橋は両岸の岩盤 に穴を開けて刎木を斜めに差込み、中空に突き 出させる。その上に少し長く同様に刎木を重ねて 行き上部構造をくみ上げ、板を敷いて橋となりま す。斜めに出た刎ね木や横の柱の上に屋根を付 け雨による腐食から保護しています。 |
| 7世紀に猿が互いに体を支えあって橋を作ったのを見て造られたという伝説があり、鎌倉時代には 既に存在していたらしいが、起源ははっきりとしていない。安藤広重の甲陽猿橋之図や、十返舎十 九の諸国道中金之草鞋などで見ることが出来ます。1676年以降に橋の架け替えの記録が残っ ています。長さ30.9m、幅3.3m、水面までの高さ30mで4層の刎ね木によって支えられています |
||
| 錦帯橋 多連式木造アーチ橋 | ||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 岩国城と城下町をつなぐ橋は、錦川の洪水によりたびたび流失していた。岩国3代領主吉川広嘉は、橋脚を無くす事で流失を避けられるとの考えから、大工の児玉九郎右衛門に、甲州の橋脚の無い刎橋「猿橋」の調査を命じた。しかし、川幅の違い(30mと200m)から刎ね橋とするのは困難であった。 明の帰化僧独立(どくりゅう)から、西湖には島づたいに架けられた6連のアーチ橋が有ることを知り、これをもとに連続したアーチ橋を構想。 児玉九郎右衛門の設計により1673年に5連のアーチ橋が完成しました。しかし翌年洪水により流失してしまい、橋台の強化をして再建したところ、改良が功を奏し、その後昭和初期まで250年以上も流失する事無く、定期的な保守・架け替え工事が行われ、その姿を保った。長さ210m、幅5mの5連式アーチ橋で、「巻き金とかすがい」の他は1本の釘も使用していない構造になっています。 錦川の「鵜飼」は有名です。 |
||
トップぺージへ 現存天守閣 国宝四城へ 日本三大桜へ


